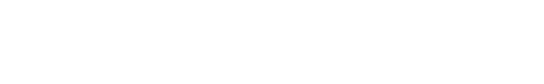ホームページをリニューアルいたしました。
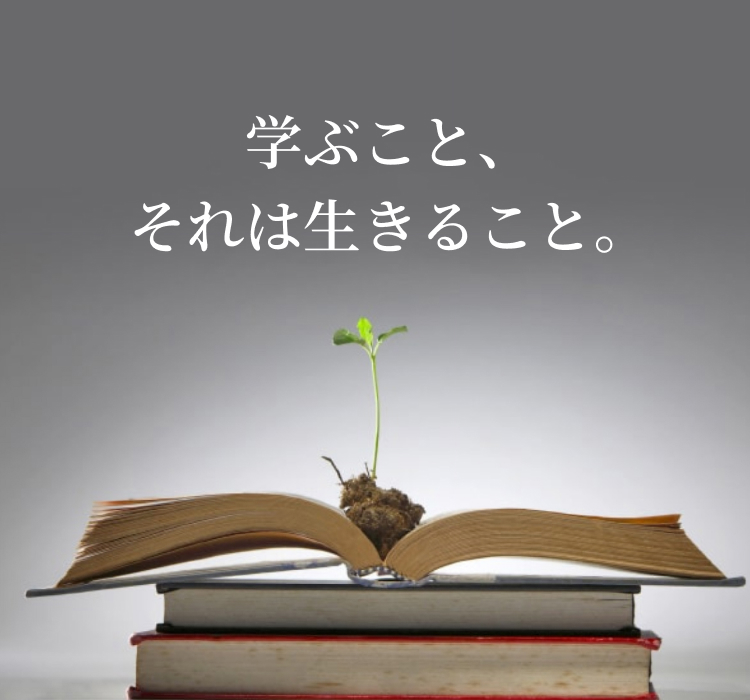
About us 森田塾について
東京都杉並区で地域密着、地域で最も古い経験と信頼の塾
生徒一人一人の進度に合わせ
塾長自らが責任指導いたします。
いつの間にか、地域で最古参の塾長になっていました。 勉強の面白さを伝えようと、個人に適った学習指導を心がけています。
30余年の間、教室を増やさず、広告宣伝をせず、口コミだけで運営してきた小さな塾です。
このホームページも塾の宣伝を目的とせず、若者には生きる力を、保護者の皆様には子育てのヒントをお届けできればと思い制作に至りました。 教育に関する、私論を書き綴っていきたいと思います。

Features 森田塾の特徴
- 地域密着、地域で最も古い経験と信頼の塾
- 塾長自らが責任指導
- 月に何度でも参加できる授業
- 少人数制で補修レベルから難関校受験まで
- 通いやすい低料金と質の高い授業

NEWS お知らせ
-
2024.03.21
Access アクセス
青梅街道 荻窪警察署前 安心して通えます!
〒167-0043 東京都杉並区上荻4-19-21-103
青梅街道沿い 荻窪警察署前(荻窪駅・西荻窪駅からバスで約7分)

Contact お問い合わせ
お問い合わせ・ご相談はお電話またはメールにて受け付けております。
こちらからお気軽にお問い合わせください。
お電話でのお問い合わせ
03-3390-3062
受付時間 平日:月~金 13:00 - 21:00